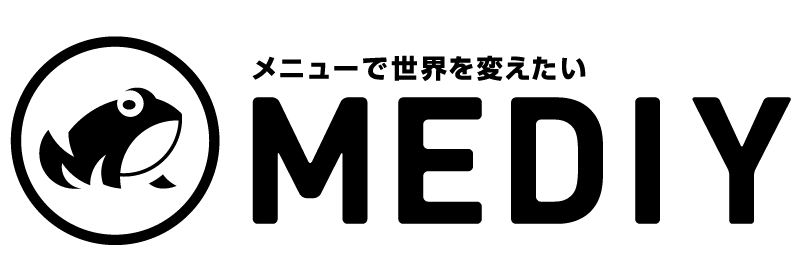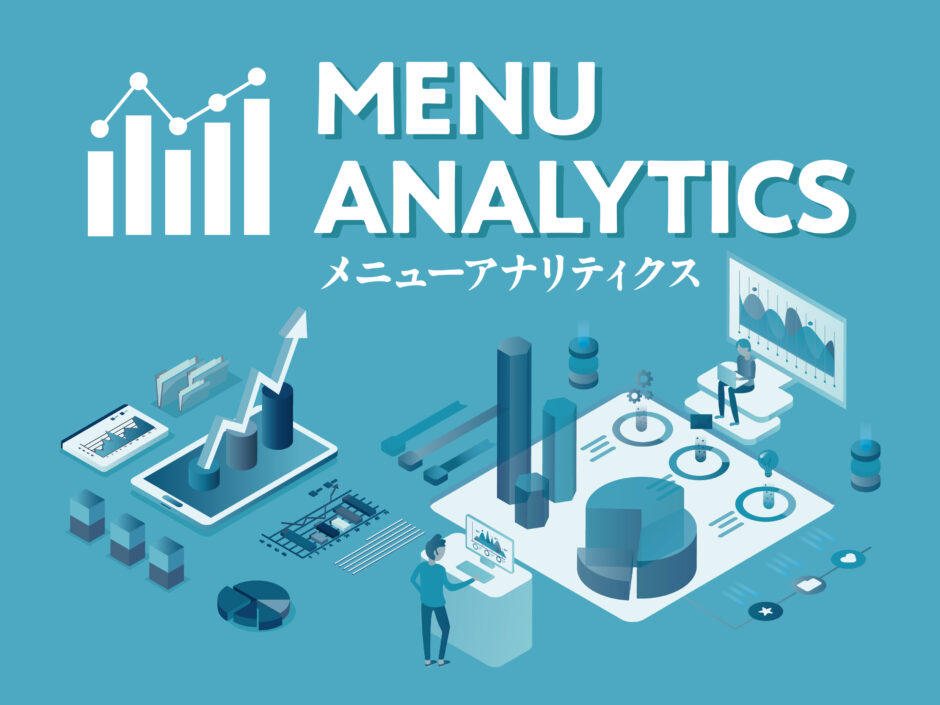飲食店DXを次のステージへ。Menu Analyticsがデータの収集・データの可視化を自動化し、KPIを設定。
数字を“行動の指針”へ変える仕組みを解説します。
データは事実、事実は誰もが共通して理解できる事
飲食店の売上を上げるためには「感覚」ではなく「データ」に基づいた戦略が欠かせません。
私たちはこれまで、【3分でわかる】メニュー分析の方法と売れるメニュー作りで、
飲食店経営におけるデータ分析の基礎を紹介してきました。
今回はその研究成果をもとに、新システム「Menu Analytics」の開発背景と、
飲食店が抱える“データ活用の壁”について解説します。

データ分析の基本フロー|飲食店DXの出発点
前回の章でも紹介しましたが、データ分析は次の5つのステップで進みます。
1. 問題の定義:何を明らかにしたいのかを明確にする
2. データ収集と前処理:複数のデータを整理・統合
3. データ可視化:グラフやダッシュボードで全体像を把握
4. データ分析:傾向を読み取り、課題や改善策を発見
5. 結果の評価と解釈:次の戦略に活かすための検証
これを、飲食店におけるデータ分析に当てはめると、
・①:売上UP・利益体質の改善
・④:目標値との客単価差異・オーダー誘導で出数構成比率のコントロール
・⑤:Before /Afterのデータを、KPIに基づいた評価・改善
です。
しかし、多くの店舗が②データ収集と前処理、そして③可視化でつまずいています。
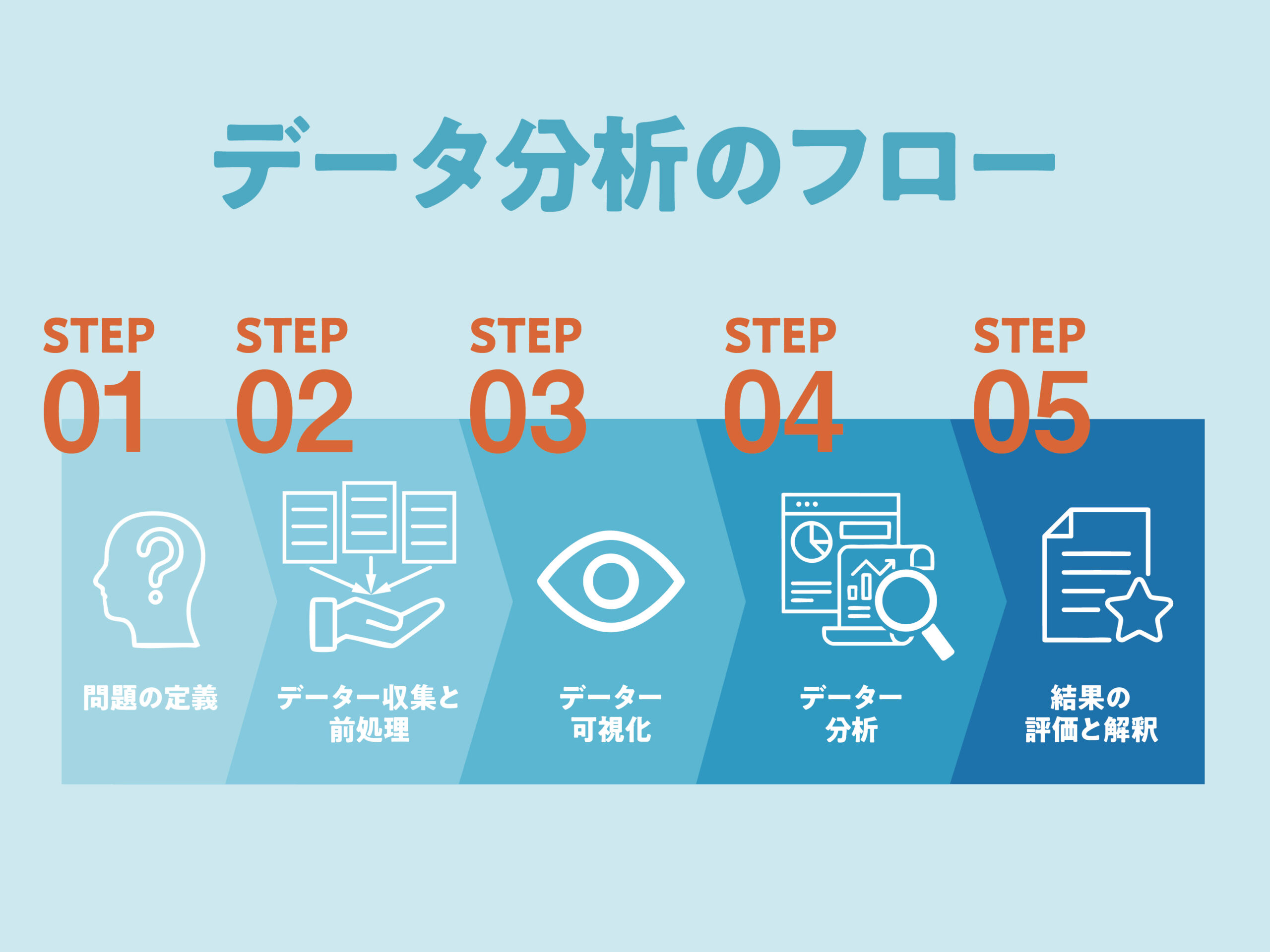
なぜ飲食店のデータ活用は難しいのか?
- POSデータの取得が手間
POSレジからデータを収集する方法は「レジロール」か「CSV抽出」が一般的ですが、どちらも抽出時点の
一時データしか得られず、手作業での取得が必要です。
その結果、日次・週次でのリアルタイム分析が困難になります。 - データクレンジングの壁
飲食店のPOSレジには以下のような分析対象にならないデータが潜まれている事が多くります。
・過去イベント商品の登録が残っている
・単価0円のお冷や過去メニューが混在
・実際に注文しているメニューとPOSレジで設定しているカテゴリーの内容が一致していない
・飲み放題と単品注文が混在している
・原価未入力商品が多数
このような状況では、正確な分析ができず、膨大な時間をクレンジングに費やすことになります。 - レポート作成が属人的
企業や店舗ごとに求める指標が異なり、Excelやスプレッドシートでの手作業で
レポート化する事に多くのリソースが奪われます。
結果的に、「データを活かす前に時間切れ」という状況に陥るのです。
Menu Analyticsが実現する“データ活用の新常識”
私たちはこうした課題を解決するために、デイリーで自動クレンジングされた
データを取得・分析できるシステム「Menu Analytics」を開発しました。
このシステムでは、
・POSレジとお客様が注文されたメニュー情報の不一致を統合
・不要データを自動除外し、分析ができる状態にデータを変換
・BIツールに自動反映し、営業結果をリアルタイムで簡単に見てわかる状態に可視化
といった一連のデータ処理を自動化し
分析者だけでなく、店舗マネージャーや現場スタッフの方も結果の確認を行えるツールとして開発しています。
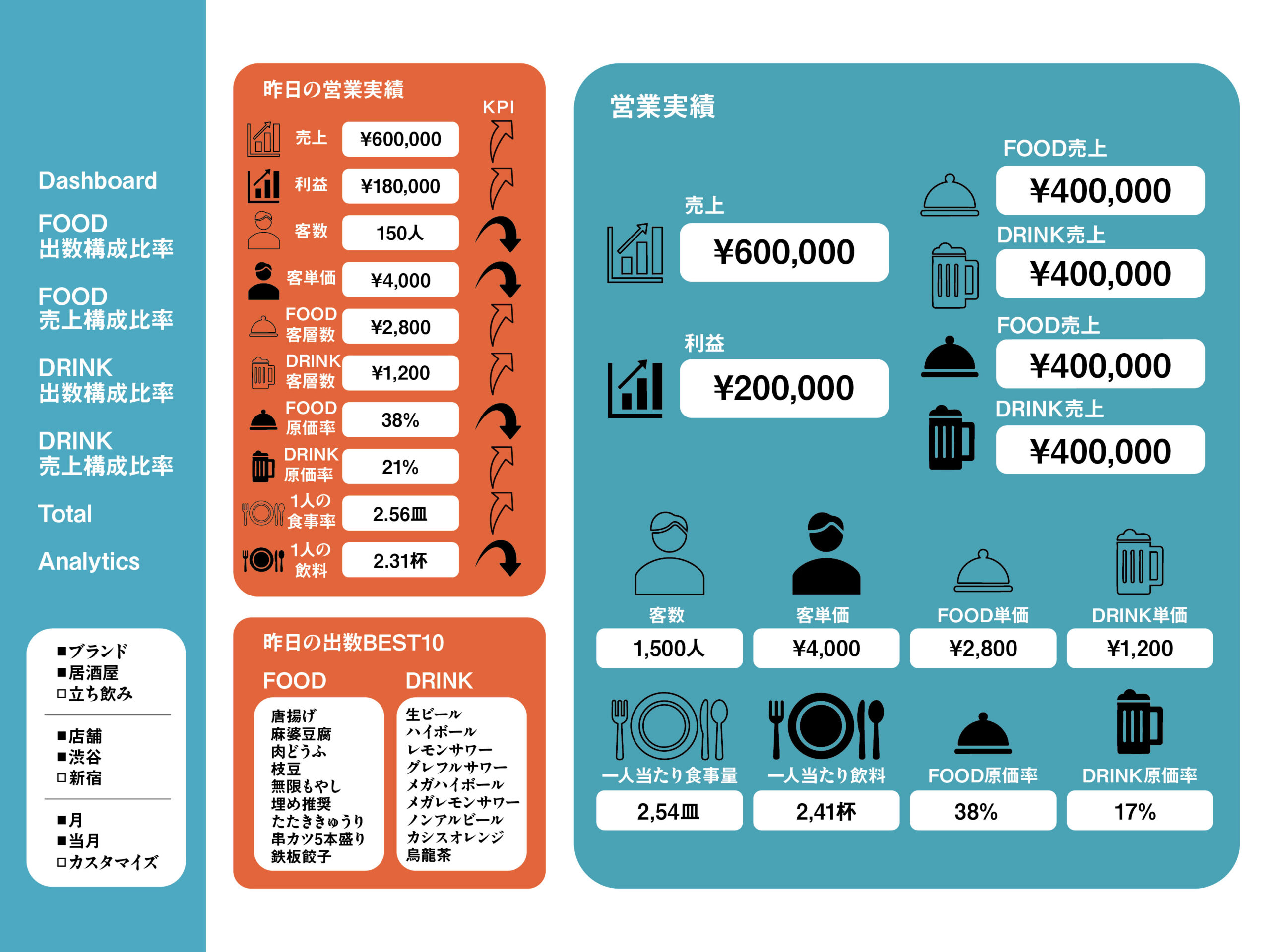
データが変える“戦略の質”
Menu Analyticsの強みは「データを“行動”に変える設計思想」です。
たとえば、
「今日も売上を上げよう」ではなく、
「昨日の一人当たりドリンク杯数が1.8杯だったので、今日は2杯に上がるように声かけを増やそう」
というように、数字が行動の根拠になるのです。
これまで「売上」が唯一の評価軸だった時代から、
「構成比・利益率・客数」のバランスを見て戦略的にお店への投資判断を行える時代へ。
Menu Analyticsは、そのための“新しい経営コンパス”です。

まとめ|データを“見るだけ”から“使いこなす”時代へ
Menu Analyticsは、これまで誰もが「わかっていてもできなかった」データ分析を、
“当たり前にできる仕組み”として提供します。
数字を見える化し、戦略を立て、行動が変わり、評価が変わり、
その連鎖が外食産業全体を変えていく。
飲食店のDXは、システム導入で終わりではなく、
「数字から目標を立てる事」と「目標に向かって人の行動変化」をつなぐところから始まります。
【第4章】データとロマンで売れるメニューを作る|デザインで魅せるモバイルオーダー戦略へつづく