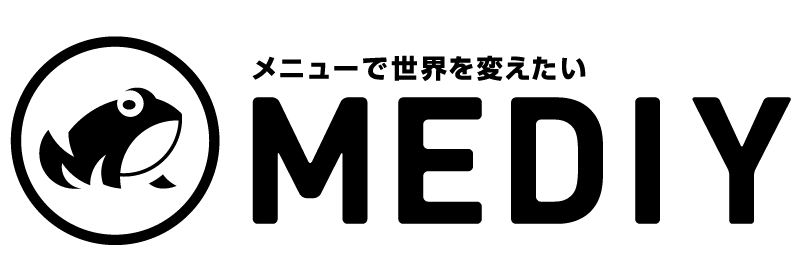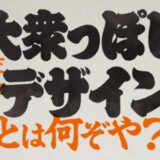令和の飲食店経営に欠かせないDX(デジタルトランスフォーメーション)。
モバイルオーダーやメニューデザインの進化を通して、アナログの温もりを残しつつデジタルで
繁盛を生む新しい飲食店の形を解説します。
令和の繁盛店は、アナログとデジタルの“いいとこ取り”で進化
飲食店DXが進む令和の時代、店舗運営は「アナログの良さを残しつつ、デジタルを味方にする」ことが求められています。
人手不足・原価高騰・SNS集客など、外食業界を取り巻く環境は大きく変化しました。
この記事では、モバイルオーダー・デジタルメニュー・SNS活用といった最新DX戦略の中から、
「紙×デジタル」の共存で生まれる“メニューデザイン”の成功法を5章に分けて紹介します。

時代が変われば、店のカタチも変わる|飲食店DXが進む理由
飲食業界は、昭和・平成・令和とともに大きな変化を遂げてきました。
今では「配膳は人からロボットへ」「宣伝はチラシからSNSへ」と、デジタルが店舗運営の中核を担うようになっています。
特に近年は、非接触ニーズやインバウンド対応などが追い風となり、飲食店DXは急速に普及。
お客様の利便性を高めながら、スタッフの負担を減らす仕組みとして注目されています。
DXの目的は“人を減らすこと”ではなく、“人を活かすこと”。
技術の導入は、接客の温度をより高めるための手段であり、負担が減った分お店の魅力(ブランド)を伝え、
ファン化を推進するようなサービスが必要であると考えます。

メニューブックも進化する。紙×デジタルの“いいとこ取り”
私たちはこれまで、紙のメニューブックでお店の魅力(ブランド)を表現し、
注文誘導で利益体質の最適化を提案してきました。
しかし今、モバイルオーダーやデジタルメニューの普及により、メニューの役割が変わりつつあります。
【紙とデジタルを共存させる時代】
– 店内では紙メニューでブランディングを伝え注文誘導
– 注文はスマホでスムーズに
– 内容更新はデジタル上で即反映
この“アナログ×デジタル”の融合が、令和の飲食店の新しいスタンダードです。
紙ならではの手持ち感で全体を把握出来る事とデジタルの利便性を組み合わせることで、
お店の魅力訴求や注文誘導と運営効率を両立できます。

モバイルオーダー市場は、飲食業の成長エンジン
モバイルオーダーは、飲食店DXの中心的存在です。
人手不足の解消、非接触対応、データ分析など、経営課題の多くを解決するポテンシャルを持っています。
【モバイルオーダー導入の3つのメリット】
1. 人手不足を補う:ホール業務を軽減し、スタッフが笑顔で接客できる時間を増やす。
2. 顧客満足度を高める:待ち時間を減らし、スムーズな注文体験を実現。
3. データを経営に活かす:人気メニューや時間帯を分析し、仕入れ・人員配置を最適化。
モバイルオーダーは単なる注文ツールではなく、経営の武器となるDX施策です。
メニューデザイン企業としての新たな挑戦
当社はこれまで「メニューブック」を通じてお店の魅力(ブランド)や戦略的な注文誘導を伝えてきました。
しかし、DXの進展によりメニューの役割の一部である注文をするというフェーズは、
モバイルオーダーが担う傾向へと変わりつつあります。
私たちは、「モバイルオーダー×メニューブック」プロジェクトを立ち上げ、
飲食店におけるUI/UXデザインの最適化と、モバイルオーダーで伝えきれないブランド価値の訴求に取り組んでいます。
紙のデザインで培った感性を、デジタルにも活かす。
それが私たちの使命であり、これからのメニュー表現のあり方です。

まとめ|時代が変われば、店のカタチも変わる
紙とデジタル、両方の魅力を掛け合わせた“いいとこ取り”の経営こそ、令和の繁盛を生み出す要です。
DXは効率化のためだけでなく、お店の魅力(ブランド)をより多くのお客様に届けるための手段であり、
そこには戦略的に設計された商品構成が必要で、”デザイン”でお客様の購買意識をコントロールする必要があります。
時代が変わっても、変わらないのは魅力的なお店(ブランド)が、繁盛店になる事。
運営効率をデジタルの力で効率化し、ブランドを未来へとつないでいくことが、
これからの飲食店DX成功の鍵になるはずです。
【第2章】モバイルオーダーのメリットと懸念点を整理する|飲食店DXの次なる課題と展望へつづく